【訪問看護の選びかた】現役訪問看護師がおススメするあなたに合ったステーションを見つける方法

訪問看護は、患者さんの生活に寄り添いながら看護を提供する仕事です。
その仕事内容はステーションによってかなり違いがあります。
どんなステーションなら自分にあうか、
訪問看護ステーションへの就職を検討するときのポイントについて解説します。
この記事はこんな人におすすめ
- 訪問看護に興味はあるが周囲に経験者がいない
- どうやって選べばいいのかわからない
- あまり経験がないけど訪問看護ができるかどうか知りたい
- 面接に行ってどんなことを質問すればいいのかわからない

この記事を書いた人
看護師になって30年以上経ちました。
訪問看護歴は17年以上です。訪問診療(診療所の医師に同行する)まで含めると20年以上になります。
3か所の訪問看護ステーションを経験しており、
現在も自転車で訪問看護を続けています。
| なりたち | 職員数 | 依頼元 | 特徴 | |
| Aステーション | 医師会のステーション | 10人以上 看護職のみ | 内科・外科・整形外科からの依頼が多い | 高齢者が多い |
| Bステーション | 診療所の訪問看護部が独立 | 5~10人 看護職のみ | 内科・外科 ターミナル 診療所のかかりつけだけでなく、他院からの依頼も受ける | 診療所が自宅での看取りをしている ターミナルが多め |
| Cステーション | 看護師が立ち上げた訪問看護ステーション | 10人以上 看護職 作業療法士数人 | 近隣の精神科病院やクリニック | 精神科がメイン 内科や外科の依頼も受ける |
時給制と訪問件数制がある
パート・非常勤の場合に、賃金の計算を時給ではなく訪問件数で
計算しているステーションがあります。
訪問件数での支払いの場合、訪問以外の仕事(研修や委員会など)の場合の
賃金がいくらになるか確認しておきましょう。
日勤のみで、休日は交代制、オンコールも交代制
というところがほとんど。
交代制だと、平日に休みがとれることがメリットです。
「○○件以上行くと報奨金が支給される」ステーションもあります。
規模やなりたちの違いと医師との連携のとりやすさ
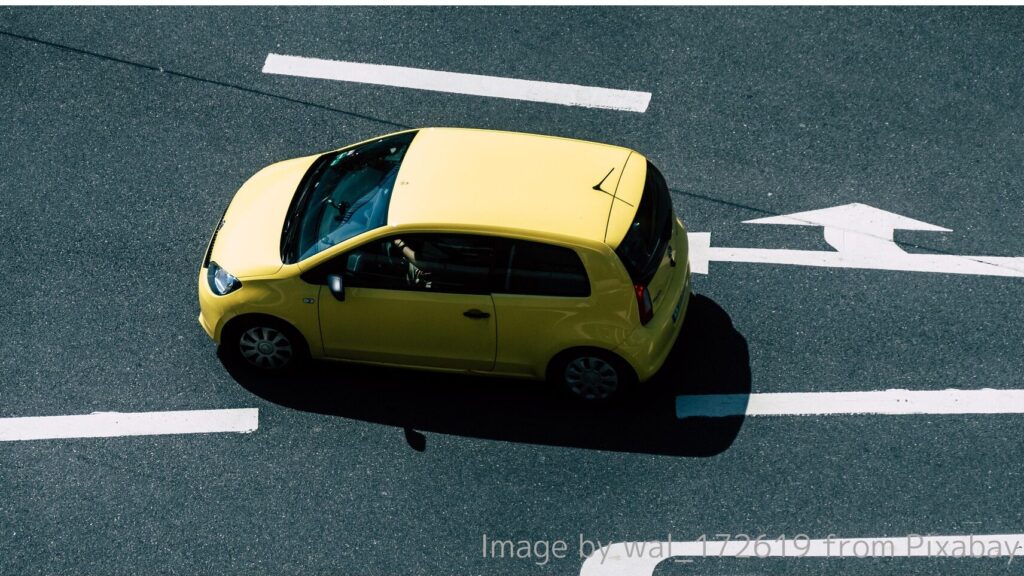
規模
設立したばかりだったり、小規模のステーションだと事務員がいないことがあります。
その場合、レセプトの処理や看護計画書・報告書を郵送するなどの
事務作業をすることになります。
そういった仕事がイヤでなければよいのですが、
利用者さんの数が増えると負担が大きくなります。
事務員がいるかどうか、いない場合の作業量なども
質問しておくのもいいかもしれません。
看護師が10人以上いると、
急な体調不良の時などに融通をきかせやすく、休みをとりやすい印象です。
設立から数年以上経過していれば、新人研修なども用意されているかもしれません。
そのステーションの教育プログラムや、
同行訪問はどれくらいおこなってもらえるかなど、
具体的に尋ねてみましょう。
なりたち
Bは小規模でしたが、母体の診療所をかかりつけにしている患者さんが多く、
医師との連携がとりやすかったです。
医師に連絡したいことがあっても診察時間帯は難しいです。
面識のない医師に電話で報告する、というのは誰でも緊張します。
その点、ステーションの母体の病院や診療所に連絡するというのは心理的ハードルが低いです。Bステーションと診療所は隣接していましたので、
外来が終わるころを見計らって報告に行ったりしていました。
系列病院のステーションに勤務の場合は、
その後のキャリア形成によっては病院勤務に戻る、
という選択肢もあるかもしれません。
生活圏内にステーションがあるときのメリット・デメリット
自宅に近い場合
メリット
①通勤時間が短くてすむのが最大のメリットです。
②自宅にトイレに寄ることができるかもしれない。
移動中、トイレはコンビニやスーパーなどで借りています。
店舗でトイレを借りるときは一応買い物をするので、
若干時間がかかることがあるのが難点です。
ルート上に自宅があればトイレを済ませることができるし、
時間帯によっては自宅で昼食を食べることもできます。
雨天・荒天の日に、この選択肢があるとないとでは全然違います。
休憩時、レインコートを脱いでそれをバッグに入れるなりしておくわけですが、
「レインコートをしまう」時に袖口や裾が濡れてしまいます。
レインコートの内側が濡れることも多いし、自分の服の袖口も濡れるのです。
自宅なら、広げて水分を拭くこともできるし、着替えることもできて、
雨の日でも快適さが違います。
ただし衛生管理の観点からは、自宅に戻るのはいかがなものか、という場面もあります
デメリット
自宅と勤務先の最寄り駅が同じですと、利用者さんと生活圏が重なる可能性が高くなります。
スーパーや駅、病院などですれ違う可能性がでてきます。
挨拶するか、知らん顔のほうがいいのか。
利用者さんとの関係性にもよるし、どれが正解というのはないでしょう。
土地柄も関係するでしょう。
挨拶するか、知らん顔のほうがいいのか。
利用者さんとの関係性にもよるし、どれが正解というのはないでしょう。
土地柄も関係するでしょう。
私はこの点はあまりデメリットと感じていないので、住居と勤務地は近い場所で選んでいます。
自宅から遠い場合
メリット
Aステーションは最寄り駅ではない距離にありました。
利用者と生活圏が重ならないので、スーパーなどで会う可能性はほぼないです。
デメリット
土地勘のない地域だと覚えるまでが少し大変かもしれませんが、
地図アプリを使えばさほど困ることはないでしょう。
直行・直帰のメリット・デメリット

Aステーションは不可、B・Cステーションは可でした。
メリット
自宅とステーション、利用者宅の位置関係によっては直行直帰ができると移動が楽です。
ステーションの担当エリアの広さとステーションと自宅との距離によっては、
直行直帰のメリットは大きいです。
デメリット
直行なら朝礼なしで訪問に入る日があるわけです。
ですのでその日の連絡事項が伝わらないことがあります。
直帰は記録を車の中か、自宅ですることになるので、
家に仕事を持って帰ることになってしまいがちです。
訪問時の移動手段の種類

入職時に普通免許を必要としているステーションは多いです。
そのほか、原動機付自転車・電動アシスト自転車、公共交通機関が使えることもあります。
A・B・Cステーションそれぞれに車・原付・電動アシスト自転車利用のスタッフがいました。
原付は渋滞の影響があまりなく、自転車は一方通行でも通行可のことが多く、
なにより駐車する場所の心配をしなくてよいことがメリットです。
私は現在は電動アシスト自転車で訪問しています。
普通免許をお持ちでない看護師さんもいらっしゃるでしょう。
求人情報に「普通免許」と書かれていても、原付か自転車で訪問することは不可なのか、
問い合わせる価値はあると思います。
「普通免許必須」となっていたら、他のステーションを探すか、
普通免許をとりに行くか検討することにしましょう。

引っ越して、自転車OKのステーションに就職する選択肢もありますよ
担当制とチーム制のメリット・デメリット
病棟勤務では担当制であっても、
自分が勤務していないときは他の看護師がみていますし、
リーダーや管理職もその患者さんのことを知っているはずです。
訪問看護で担当制だと、その人のことを知っているのが自分だけ、
という状態になりがちです。
担当制
メリット
日々の訪問の道順が固定されるので、毎朝ルート確認をしなくてよいので楽です。
デメリット
その利用者さんのことを良く知っているのが自分だけ、という状態になります。
祝日の振替えの訪問や、自分が有給休暇をとりたいときに、
他のスタッフに依頼することが難しくなります。
「いつもの看護師さんでないと緊張するからいやだ」というふうになりがちです。
対策
その利用者さんのことを知っているのが自分だけ、
という状態にならないようにします。
具体的には、初回訪問に二人で行くようにする、
違うタイミングで他のスタッフと一緒に訪問する、などです。
日々の変化などについては、もちろん上司に報告しているのですが、
あれこれ話し合うことのできる同僚の存在は大きいです。
その利用者さんに一度でも会ったことのある同僚だと、
ニュアンスが伝わりやすくて相談しやすいです。

そもそもひとりで訪問するのが不安です
最初の1~3か月は同行訪問(先輩と一緒に行く)しますので、
見て学ぶことから始めることができます。
少し慣れてきたら、状態が安定している利用者さんや、
自分が経験してきた診療科の利用者さんから担当させてもらうようにすれば、
少しは安心して取り組めるのではないでしょうか。
あるいは、週2回以上の訪問をしている利用者さんを担当すると、
曜日を分けて先輩と一緒に担当することになりますから、
相談しやすいし、心強いものです。
チーム制
メリット
急病で休みのことがあっても、スタッフ全員でカバーしていくので少し気が楽です。

担当制であっても皆で振り分けて訪問するのは同じなのですから、
実際には気分の問題かもしれません。
利用者さんのことを担当しているのが自分だけではない、
というのは担当制よりは負担が少ないです。
デメリット
小規模なステーションでの導入は難しいようです。
オンコールは夜勤より負担は少ない(かもしれない)

オンコール対応は事業所によって、電話の回数や実際に出動する頻度に違いがあります。
パートならオンコールなしにできる職場はわりとあります。
私は現在ワークライフバランスのためにパート勤務、オンコールなしです。
電話がかかってきた時に「話を聞いてどのようにするか説明する」だけですむように
看護計画を立て、訪問看護を提供していきます。
それでも実際に出動しなければならないこともあります。
とはいえ、実際の出動は多くはないです。
Aステーション・Bステーションでは月に1~2回、
Cステーションでは年に1回あるかないか、です。
ステーションによってはもっと多いこともあるようですので、
面談のときに具体的に質問するといいと思います。
出動回数多めで、翌日も通常通り勤務だと体力的にきつくなるかもしれません。
どれくらいなら許容範囲か考えておきましょう。

経験のない「オンコール」を不安に思うのは当然です。
電話対応だけの時の賃金、実際に出動したときの賃金、
出動時の交通手段、タクシー利用時に経費にできるか、など
確認しておくとよいでしょう。
オンコールを持つと、「お酒を飲めない」「遠くへ外出できない」など
制約はありますが、夜勤と違って自宅ですごすことができます。
ひと晩に1度も電話がかかってこない日もあります。
緊張するでしょうが、体力的な負担は夜勤ほど大きくないでしょう。
営業は事業が軌道にのるまで

【営業とは】開設してまもないステーションでは、新規利用者さんの獲得のために
近隣の病院や施設などに挨拶に行くことです。
自分のステーションでどういう看護が提供できるか、特色などを説明して
自分のステーションを知ってもらい訪問看護の依頼をもらうことが
経営の安定のために必要です。
この「営業」がイヤでステーションをやめてしまう看護師さんもいらっしゃいます。
私見ですが、管理者でないのならば、
「営業には行きたくない」と言っていいんじゃないでしょうか。
「訪問看護は営業が重要である」「経営を安定させるためには必要」
これは経営する側から当然の考え方です。
しかし、看護教育の中に経営は含まれていません。
営業職や自営業の経験がなければ、「自分が営業に行く」ということに
抵抗を感じる人がいるのはしかたのないことでしょう。
事業が軌道に乗れば、充分忙しくなるのですから、
営業させることで看護師さんがいなくなってしまうのはもったいないことです。
訪問看護は若手も歓迎

以前は、「訪問看護は何年か病棟を経験してから」という意見が優勢でしたが
最近は若手の育成に力を入れているところもあるようです。
私が勤めているステーションにも、ほぼ新卒で入職されて、
立派に勤められている看護師さんがいらっしゃいます。
電話で連絡するしかなかったころに比べ、
端末で連絡をとれば電話よりも早く、手軽に相談できるようになりました。
画像をみてもらいながらアドバイスしてもらう、ということもできます。
相談しやすい環境が整ってきて、働きやすくなっているのではないでしょうか。
まとめ
訪問看護は手ごたえのある仕事
利用者さんと1対1でじっくり関わりたいと考えている看護師さんには、
訪問看護はやりがいのある仕事です。
病棟と違い、ひとりで対応することが多いので、
自分に合うステーションを選ぶことが重要です。
小児科や精神科に特化していたり、
利用者層や提供サービスに特色を出しているところもあります。
経験が足りないかも、と感じていても
自分が経験してきた分野、興味のある分野を選ぶことで
よりよい転職ができるのではないでしょうか。
転職活動はいい経験になる

向いてなかったらどうしよう。勇気が出ない。

「向いてない」と感じたとしても、
そのステーションの方針と合わなかっただけかもしれません。
訪問する仕事が向いてないとわかったとしても、
それはそれであなたの貴重な経験です。
病院に戻っても、患者さんの自宅での生活を知ったあなたは
それまでとは違う視点で看護していけるのではないでしょうか。
あらためて病院勤務するもよし、看護小規模多機能型などを検討するもよし、
企業や学校・保育園など、看護の仕事はあらゆるところにあります。

転職活動は、いまの職場に勤めながらできるし、時間をかけていいのです。
じっくり探した方がよいのはもちろんですが、
転職活動をすることで
気持ちに余裕がうまれることもあります。

次への一歩を踏み出したよ!という行動が前向きにしてくれる
ハローワークの求人も利用したことがありますが、
いざ面接に出向き、具体的な話をしてみると、
条件などが少し違っていて不成立になったことがあります。
具体的には、
訪問看護部の求人なのに、「まずは病棟で働いてほしい」とか
事務員がいないから「レセプトなどの事務作業もあります」 とか
要普通免許 と書いていないのに、「普通免許をとってくれ」 とか
いろいろありました。
採用側にしてみれば、
求人票を出してから時間が経過して事情が変わっていたのかもしれませんが、
お互い時間の無駄になりました。
- 詳しい情報を知りたい
- 条件のすりあわせをしたい
- まだいろいろ迷っている
という状態のときは、「面接して担当者と話ができるエージェント」がいい
と思います。
私が利用したことのあるこちらをおすすめします。↓
求人サイトによって違う病院・施設の求人がありますので、
2~3サイト登録してみるほうがよいです。
履歴書などの手続きがオンラインで完結できます。
希望するエリアや転職先の種類などを登録しておくと、
条件のあう病院や施設の方からスカウトメールが来ることがあります。
面接を申し込むのに心理的ハードルが少し下がる気がするのでこちらもおすすめです。↓

