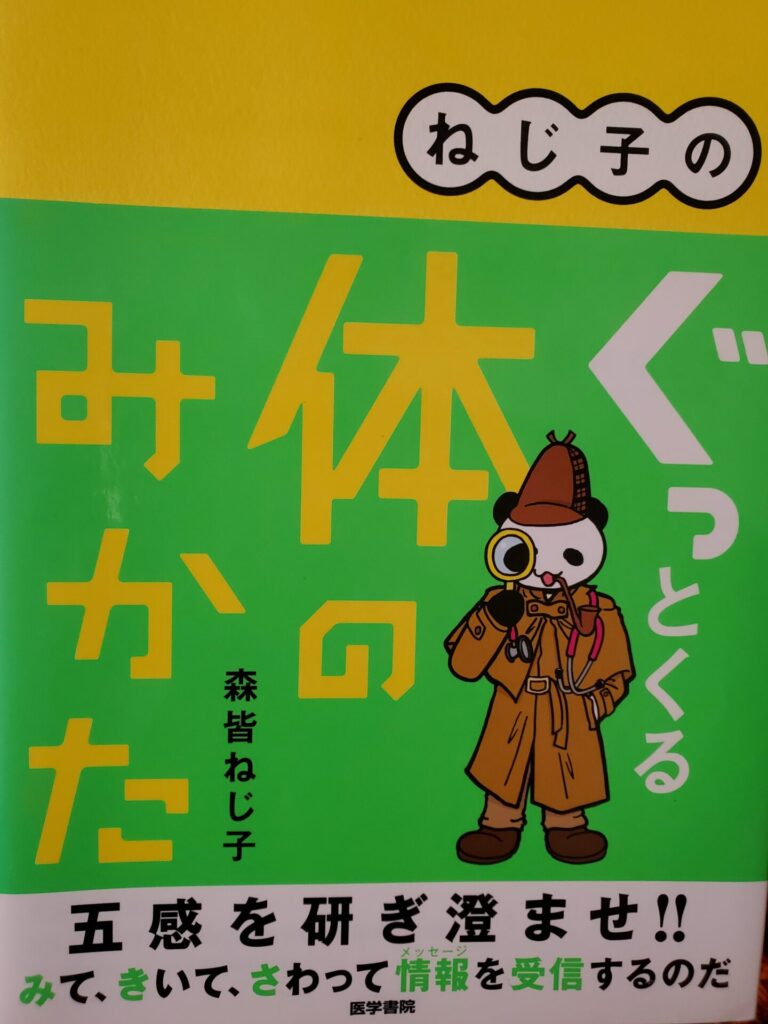フィジカルアセスメントを実践的に復習|『ねじ子の ぐっとくる体のみかた』

患者さんの変化を見逃してしまったのでは、と思うと怖いし、
新人のころにはとても不安になるものです。
- 急変の前兆を見逃したのではないか
- 入院時の観察項目を見落としたのではないか
- 優先してみるべきポイントをはずしたのではないか
全身くまなく観察、と学びますが、どんな技術を使うかは
勤め先によって差がでます。
頻繁におこなう技術は慣れるけど、めったに見ない技術もあります。
現場で教えてくれる先輩がいる人は幸運ですが、そうとも限りません。
学習したうえで経験を積むことが必要ですが、病棟はいつも多忙。
一から十まで教えてもらうことってほぼ不可能です。
そこで、おすすめなのがこの本です。
実践的なフィジカルアセスメントを学ぶ
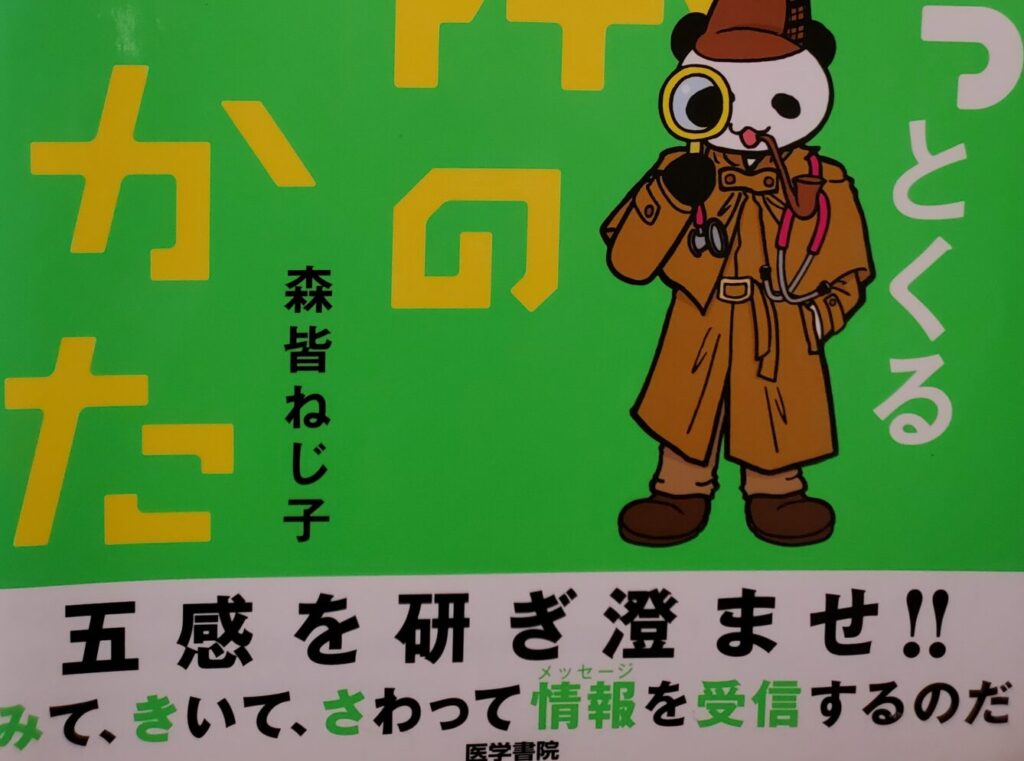
イラストが豊富で、フィジカルアセスメントを実践的に学べます。
訪問看護や病棟でも、すぐに活かせる知識が詰まっています。
病棟でも訪問看護でも機会が多い、のど・胸部・腹部について詳しく説明されています。
頸のみかた
学生時代、「項部硬直」がテストに出ました。
事柄としては知っているけれども、実際にどのような手技で実施するのかは
当時は習いませんでした。
甲状腺やリンパ節のみかたについてもイラストでわかりやすく解説があります。
こちらも学生時代には習いませんでしたが、
リンパ節は現場で勉強しました。
発熱や倦怠感など、使える場面の多い手技です。
日常使わなかったとしても、できるようにしておけば役にたつ機会はきっとあります。
胸のみかた
音源付きの教材で勉強したことがある人は多いと思います。
心音については、循環器や集中治療室でなければ、
継続して勉強する機会は少ないかもしれません。
肺については、いつも聴くような部署でないかもしれません。
必要にせまられたときの予習・復習にちょうど良いボリュームです。
腹のみかた
盲腸や帝王切開くらいは手術じゃない、と思っている人もいるので注意。口では「手術したことない」って言ってたのに、お腹を見てみたらオペスカーがー!!ってよくあることです。手を抜かず自分の目でみよう。 引用 ねじ子のぐっとくる体のみかた 100ページ
これと同じ経験があります。
教科書には、必ず全身を観察するようにと書いてあるのですが、
入院時や初回訪問時は実施することが沢山あるので、
患者さんを裸にして全身見ている時間がないことがあります。
初回の訪問で無理だったときには、2回目以降で必ず見るようにしています。
仕事で忙しい毎日でも、この本ならスキマ時間で学ぶことができます。

患者さんの状態の変化を感じた時に、
まず自分で確認してみることができるようになります。
これって、とても自信につながることではないでしょうか。